享保年間の1717年に近江出身の渡辺伊兵衛が、寺町二条に茶、茶器を扱う店として「近江屋」を出したのが始まりで、やがて宮家の一つ、山階宮より「茶、一つを保つように」と「一保堂」の屋号を賜ったのが名前の由来です。寺町二条、京都市役所の北側にある骨董品店が建ち並ぶ一角に一保堂がある。いかにも老舗の日本茶の専門店という感じで歴史と風格が伝わって来ます。取材後に建物がリニューアルされたが、見事なくらいそのままに見た目が変わっていないのに感心しました。
お茶を買う目的で来られる方が大半でしょうが、お店の中には喫茶室嘉木が併設されており、自分でお茶を点てられるんです。初めてお茶を点てる方でも店員さんが教えて下さるので、心配ありません。抹茶、玉露、煎茶、ほうじ茶、玄米茶などが選べて、生菓子が付いています。せっかくなので抹茶を点ててみることにしました。素人ではうまく説明できないので、お店のサイトで分かりやすく解説されていたのを引用させていただきました。
抹茶の点て方
お茶の葉を石臼で挽いて微粉末にしたものが抹茶です。鮮やかな緑色とまろやかなうまみの中にさまざまな成分がたっぷり。急須で淹れるお茶と違って、抹茶はお茶の葉をそのまま口にすることになるので、お茶のもつ良さをあますところなく取り入れることができます。
一 、抹茶茶碗に抹茶を茶杓で1杯半(約2g)
茶杓とは、抹茶をすくうために竹で作られた道具のこと。ティースプーンでも代用できますが(山盛り1杯が目安)、においや湿気を嫌うデリケートな抹茶だけに、茶杓があれば安心です。
二、別の茶碗に一度お湯を注ぎ、抹茶茶碗に移し替える。
抹茶の持ち味を引き出すお湯の温度は約80℃。熱湯をまず別の茶碗にとって、抹茶茶碗に移します。このとき抹茶茶碗もあらかじめ温めておくとよいでしょう。抹茶茶碗に三分目くらいが適量。そっと移し替えて。
三、抹茶を点てる
茶筌で抹茶とお湯をまんべんなくかき混ぜます。英文字の「m」の字を描くように動かせるのがコツ。ダマが目立つ場合は、茶筌の穂先でダマをつぶしながら点ててください。
四、抹茶がお湯に混ざれば出来上がり。
抹茶は砂糖や塩のような結晶物と違って、水には溶けません。じゅうぶんに撹拌できたら、抹茶が温かいうちに、お楽しみください。表面に「の」の字を描いて、茶筌をそっとひきあげるのがコツ。
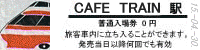
|

|
|
CAFE
LIST 京都のカフェ ★★★★☆ 自分でお茶を点てられます |
| SHOP | 一保堂茶舗京都本店・嘉木 |
| 住所 | 京都市中京区寺町通二条 上ル常盤木町52 |
| 電話番号 | 075-211-3421 |
| 営業時間 | 09:00〜19:00(日祝は6時まで) 喫茶室嘉木 11:00〜17:30 |
| 定休日 | 休まず営業(正月を除く) |
| HP | http://www.ippodo-tea.co.jp/ |
| 取材年月日 | 2003年1月13日 |
 一保堂茶舗京都本店外観1 |
 一保堂茶舗京都本店外観2 |
 ゑびす神社の初戎の飾り |
 打ち水された中庭が清々しいです |
 覚束ない手つきでかき回しています |
 何とか出来上がりました |
町田カフェ | 横浜カフェ | 東京カフェ |
松本カフェ | 草津カフェ | LINK
All Rights Reserved, Copyright (C) Mabumaro